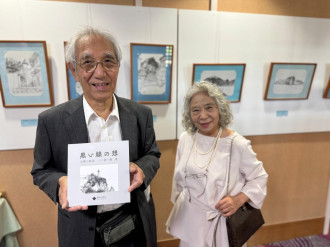地域に根ざして自家栽培され今日まで志摩市で育てられてきた伝統野菜・在来品種の「水ナス」が現在、収穫の最盛期を迎えている。
伝統野菜とは、特定の地域で古くから栽培され受け継がれてきた野菜のことで、在来品種、固定種とも呼ばれている。種子を採って次の年に種子をまき、自家採種を繰り返すことで、その土地の気候風土に適応して生まれた野菜を言う。大量生産される野菜とは異なり、栽培に手間がかかり、生産量が限られるため、その地域だけで消費されることが多い。近年、その希少性や地域の文化を伝える食材として注目を集めている。
水ナスと聞くと、大阪南部の泉州地域で栽培される濃い紫色で皮が薄く丸い形で、あくが少なく甘味があり生でも食べられるほどみずみずしいのが特長の「泉州の水ナス」が知られている。志摩地域で栽培される水ナスは、一般的なナスの形をしているが、色は薄い紫色、食べると泉州の水ナス同様にあくが少なく甘みがありみずみずしいのが特長。地元では「鵜方(うがた)の水ナス」、「しまむらさき」、単に「水ナス」などとよばれている。農業生物資源ジーンバンク(つくば市)の在来品種データベースによると「鵜方の水なすび」として登録されている。
志摩市阿児町で50年以上農業を営む田畑清江さんは「毎年5月の初めに種をまき、中頃ポットに植え替え、苗が20センチほどになった頃に定植し、7月に入った頃からできた水ナスを順番に出荷している。シーズンで一番大きく元気のある水ナスを来年の種用に網をかけて覆い保護し残している。友人らに種子を分けて、その人たちも水ナスを作ってくれている。とてもおいしいナスなので、先人たちが代々つないで残してくれた大切な種子をこれからも大切に守り続けていきたい」と話す。
三重県農業研究所(松阪市嬉野川北町)生産技術研究室の小西信幸さんは「三重の伝統野菜では『三重なばな』がブランド化に成功し、日本一の出荷量を誇るまでになった。蕾がなくほろ苦く茎が柔らかいなど、冬の野菜として人気が高く全国に出荷している。しかしながら生産者の高齢化などから生産量は減少傾向に。農業研究所では、効率的に生産量が確保できるように、今年から機械化による試験栽培を初めるところ。『鵜方の水なす』は生産量が少ないため、ほとんどの人がまだ食べたことがないのでは。種子を継承し生産量を確保し、多くの人に食べてもらうため、生産者が結束しブランド化を目指し、行政などと連携しながら取り組むことも必要では。以前、伊勢の伝統野菜の『朝熊(あさま)小菜』を松阪の農業研究所で作ってみたことがあったが、栽培環境が異なったためか、朝熊小菜と同じような生育をしなかった。伝統野菜は気候や土壌など地域の環境が育てた野菜でもあるので、地域の人が大切に育てていくことが重要」と話す。
水ナスは、志摩市内のスーパーぎゅーとらラブリー鵜方店、イオン阿児店、肉よし(以上阿児町)、恵みの郷 志摩街道(磯部町)などで購入できる。