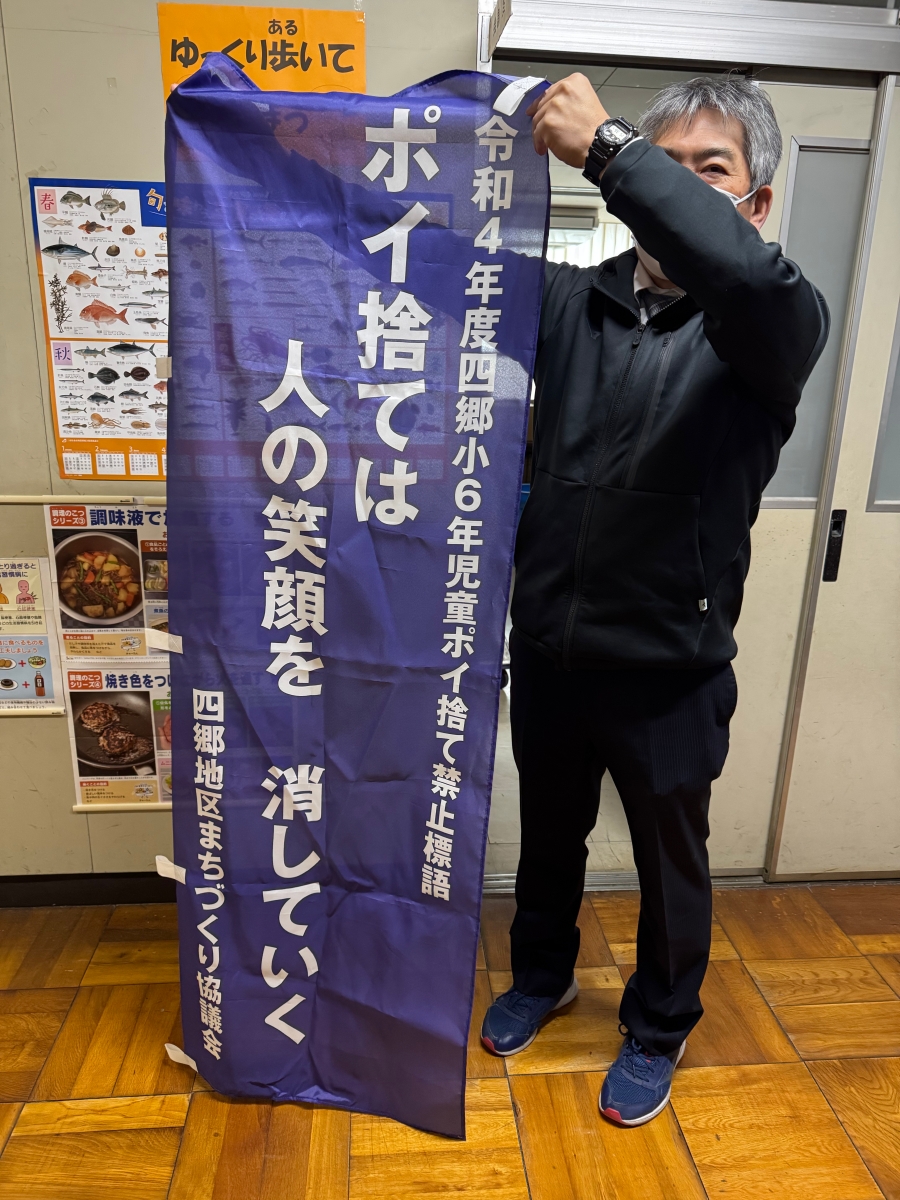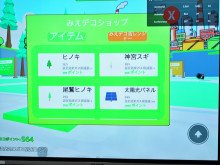志摩市で農業を営む稲田武久さんの農園(志摩市磯部町)のナシが現在、四方に伸びた枝にたわわに実って出荷を待つばかりとなっている。
稲田さんは、幸水、豊水、南水、秋月、秋麗、にっこり、甘太など約10種類のナシを栽培し、出荷前に「電子水」を約10日間散布し「電子梨」として販売する。
電子水は、水に特殊な技術を使いマイナスの電気を流した水(=静電気を帯びた水)のこと。稲田さんは「環境汚染問題について書かれた有吉佐和子さんの長編小説『複合汚染』を読んだことをきっかけに、できるだけ農薬を使わない栽培方法はないかと考え、さまざまな方面から知識を得て、楢崎皐月さんの『静電三法』理論にたどり着いた」と話す。その後、研究を重ね、電子水を散布する栽培方法を編み出したという。稲田さんは「実のざらつきがなくなり、肉質がよく、水分が多くなるのが特長」と話す。
稲田さんは「昨年は体調を崩し、ナシの木の手入れができなかったので、ほとんど出荷できなかった。『無理をさせてはいけない』とナシの木が体を気遣い配慮してくれたのだと感じた」と打ち明ける。「今年の最初の収穫は『なつしずく』という品種で、『幸水』よりも早く実がなるのが特長。今は『幸水』の収穫だが、一番おいしい状態で届けたいと思うと、もう少し収穫を待った方が良さそう。中元にと既に多くの注文をもらっているが、自然相手なので、人間の都合通りにならないのも事実」と苦笑する。
約70年前に稲田さんの父が植えたナシの木を大切に管理しながら、ナシの栽培に最善を尽くす稲田さん。「地場産業の真珠養殖で冬場に廃棄されるアコヤ貝の身の部分をもらい、EMぼかしを作り肥料にしたり、電子水を散布したり…。さまざまな工夫を凝らしながら安心安全でおいしいナシを作りたいと取り組んでいる。今も試行錯誤の連続。自然は偉大で思うようにいかないが、問題解決のために考え試すこともまた楽しい。予想しない感想をもらうのもうれしい。今は酵素を研究中で、調べれば調べるほど、また面白い」とも。